中日ドラゴンズ英智と中小企業経営
2014/07/23(水)
 近年のクラウドサービスの普及に伴い、企業の業務効率化や新規ビジネス創出を支える基盤として注目を集めているのが「SaaS(Software as a Service)」です。
近年のクラウドサービスの普及に伴い、企業の業務効率化や新規ビジネス創出を支える基盤として注目を集めているのが「SaaS(Software as a Service)」です。
利用者はインターネットを通じて必要な機能をすぐに利用できること、従来のオンプレミス型システムに比べて、導入コストや運用負荷を大幅に軽減できることが特徴です。
一方で、SaaSを新たに開発・提供する企業にとっては、堅牢なセキュリティや柔軟なスケーラビリティを備えたシステムを構築する必要があるため、信頼できるシステム開発会社の存在が欠かせません。
そこで本コラムでは、SaaSの基本から開発プロセス、個人開発の可否、システム開発会社の選び方、そしておすすめのSaaS開発会社10社を厳選してご紹介します。SaaS開発を検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

SaaSとは「Software as a Service」の略で、クラウド環境上で提供されるソフトウェアを、利用者がインターネット経由で利用できるサービス形態を指します。
従来のようにパッケージソフトを購入・インストールする必要はなく、ブラウザやアプリからすぐに利用できます。代表的な例としては、Google WorkspaceやSlack、Salesforceなどが挙げられ、業務効率化やコミュニケーション、営業支援といった幅広い用途で活用されています。
企業にとっては、初期投資を抑えつつ、常に最新の機能を利用できる点が大きなメリットです。また、利用者数やストレージ容量を柔軟に調整できるため、スタートアップから大企業まで規模を問わず導入が進んでいるのです。
SaaSとよく比較されるのが「PaaS(Platform as a Service)」や「IaaS(Infrastructure as a Service)」です。
SaaSは完成されたアプリケーションをそのまま利用できるサービス形態で、ユーザーはシステムの構築や運用を意識せずにソフトを活用できます。
一方、PaaSはアプリケーションを開発・運用するための基盤を提供するサービスで、開発者はプラットフォーム上で独自のアプリを構築することが可能です。
また、IaaSはサーバーやネットワーク、ストレージなどインフラ部分をクラウドで提供する形態を指します。柔軟な環境構築ができる反面、システム設計や管理は利用者側に委ねられます。
以上をまとめると、IaaSは「インフラを借りる」、PaaSは「開発基盤を借りる」、そしてSaaSは「完成したアプリを借りる」という点に違いがあります。

SaaS開発を成功させるためには、単にアプリを作るだけでなく、「安定稼働し続ける仕組み」を構築することが欠かせません。
ここでは、SaaSの代表的な開発プロセスを、段階ごとに確認していきましょう。
SaaS開発における最初のステップは、要件定義です。SaaSとして提供する機能やターゲットユーザー、利用シーンを明確にし、サービス全体の方向性を固めます。
例えば「どの課題を解決するのか」「ユーザーはどんな機能を求めているのか」を整理し、MVP(最小限の実用的な製品)の範囲を決めていきます。
要件が曖昧なまま開発を始めると、後の工程で仕様変更が増えてコストや工期に影響するため、丁寧なヒアリングと市場調査が欠かせません。
要件が固まった後は、システム設計に進みます。
設計では「ユーザーが同じ基盤を共有するマルチテナント設計」「スケーラビリティを考慮したクラウド環境設計」「セキュリティ対策の実装方針」など、SaaS特有の要素を盛り込みます。
また、UI/UX設計も重要です。直感的に使えるデザインや快適な操作感を実現できるかどうかが、サービスの継続利用に直結します。
設計が完了すると、いよいよ実装フェーズに入ります。
SaaS開発では、PythonやRuby、JavaScript(特にReactやVue.js)、PHPなどの開発言語がよく利用されます。また、クラウドインフラにはAWS、GCP、Azureといった主要クラウドサービスが選ばれるケースが一般的です。
この段階では、設計書をもとに機能をコーディングし、サービスとして動作する形に仕上げていきます。開発効率を高めるために、アジャイル開発を採用するケースも多く見られます。
実装後は、SaaSのサービスが正しく動作するかを検証するテストを実施します。
SaaSの場合、単体テスト・結合テスト・負荷テスト・セキュリティテストなど多角的な検証が欠かせません。特にクラウド環境では、アクセス集中や多様な利用環境に対応する必要があり、テストの質がサービスの信頼性を左右します。
テストを通じて不具合を洗い出し、修正と再検証を繰り返すことで品質を高めていきます。
最終段階は、SaaSのリリースと運用保守です。
SaaSをリリースすることは、あくまで「スタート」であり、「完成」ではありません。ユーザーからのフィードバックをもとに継続的に改善をおこない、機能追加やセキュリティアップデートを重ねることで、競争力を維持していきます。
また、障害対応や稼働監視、バックアップ体制の整備も必須です。運用運用をしっかり実施することで、ユーザーに安心して使い続けてもらえるSaaSへと成長します。

「SaaSは個人でも開発できるのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。
結論からいえば、技術力や知識があれば個人開発は可能です。実際に、個人が立ち上げたサービスが成長して事業化した事例もあります。
しかし、SaaSには「セキュリティ」「スケーラビリティ」「安定運用」「法令遵守」など、多面的な課題が存在します。小規模なMVPであれば個人でも挑戦できますが、本格的に事業化を目指す場合は、専門的なノウハウを持つシステム開発会社に依頼するのが現実的です。
特に、決済や個人情報を扱うサービスでは、法的要件やセキュリティ基準を満たさなければならず、経験の浅い個人開発ではリスクが高まります。
そのため、本格的にSaaS事業を成功させたいのであれば、経験と実績を持つシステム開発会社に依頼するのが現実的で安心でしょう。プロのシステム開発会社であれば、要件定義から設計・実装・運用保守まで一貫して支援してもらえるため、リスクを抑えながらスムーズに事業化を進められます。
SaaSを成功させるためには、アイデアや企画力だけでなく、安定した技術基盤と継続的な運用体制が欠かせません。とはいえ、自社だけでゼロから構築するのは難しく、多くの企業がシステム開発会社に依頼しています。
ここでは、SaaS開発に強みを持ち、実績やサポート体制に定評のあるシステム開発会社を10社厳選してご紹介します。特徴や得意分野を比較しながら、自社のサービスに最適なパートナー選びの参考になさってください。

画像出典:フレシット株式会社HP
フレシット株式会社は、SaaSに特化したシステム開発会社として、企画段階から収益化までを見据えたサービス設計を支援しています。
業務効率化や経営強化を目的としたSaaS開発に強みを持ち、構想力と技術力を兼ね備えたチームで理想のサービスを形にします。
構築から運用まで一貫して任せられる安心感が魅力のシステム開発会社です。

画像出典:VeBuIn株式会社HP
VeBuIn株式会社は、日本とインドの強みを組み合わせたハイブリッド体制を採用するSaaS開発会社です。
最適なアーキテクチャ設計やスケーラビリティ、セキュリティ対策まで一貫して提案し、競争力のあるSaaS構築を実現します。
オンサイトとオフショアを組み合わせた柔軟な体制で、継続的な運用保守にも対応できる点が強みです。

画像出典:オルグローラボ株式会社HP
オルグローラボ株式会社は、ラボ型開発を強みとするシステム開発会社で、SaaS開発にも柔軟に対応できる体制を備えています。
クライアントと密に連携しながら進めるスタイルが特徴で、要望の変化にも迅速に対応できます。
グループ会社との連携による豊富なリソースを活かし、スキルマッチしたエンジニアチームを構築できる点も魅力です。
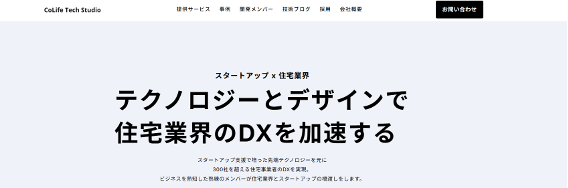
画像出典:株式会社CoLife HP
株式会社CoLifeは、スタートアップ向けにバーティカルSaaS開発を数多く手がけるシステム開発会社です。
不動産・人材・飲食・金融など幅広い業界に対応し、業務ドメイン知識を効率的に習得するオンボーディング体制を整備しています。
競合調査や現場理解を踏まえた提案力を強みとし、スピードと品質を両立したSaaS開発が実現できます。

画像出典:株式会社SaaS HP
株式会社SaaSは、豊富な開発実績とノウハウを活かし、効率的かつ価値あるSaaSを提供するシステム開発会社です。
CMSやECサイト、マッチングプラットフォームなど大規模WEBアプリケーションの開発に強みを持ち、スマホアプリにも対応しています。
要件定義から設計、プロジェクトマネジメントまで一貫して支援できる体制が整っている点も安心です。

画像出典:株式会社システムズHP
株式会社システムズは、製造・流通・金融など多様な業種向けに最新技術を融合したシステム開発をおこなうSaaS開発会社です。
オンプレミスからAWSなどのクラウドまで幅広く対応し、構想提案から運用保守まで一貫支援に定評があります。
SaaS開発ではスクラッチ開発だけでなく、ERPカスタマイズやテンプレート活用など柔軟な提案力が強みです。

画像出典:株式会社ダイナックスHP
株式会社ダイナックスは、自社開発・自社運用のSaaSに特化するシステム開発会社です。
長年にわたり「通禁オフィス」「会員管理『なかま』」など多様な業務特化SaaSを手掛け、高い構想力と設計力を誇ります。
WEBシステム開発に精通し、企画からリリースまで一貫対応できる体制が魅力です。

画像出典:Tokyo Tech Lab株式会社HP
Tokyo Tech Lab株式会社は、多様な業界に対応したSaaS開発を得意とするシステム開発会社です。
リテールや教育、金融、ヘルスケアなど幅広い分野において、ERPやCRM、LMSなどのアプリケーション構築を支援しています。
プロダクト戦略からUI/UX設計、セキュリティ監査、リリース後の運用保守までフルサイクルで対応し、クラウド移行や追加API開発といった柔軟なサポートも可能です。

SaaSの開発を成功させるためには、依頼先となるシステム開発会社の選定が重要です。
ここでは、SaaS開発会社を選ぶうえで、確認すべき代表的な5つのポイントについて確認していきましょう。
SaaS開発会社によって提示される料金体系はさまざまです。代表的なのは「固定価格型」「時間単価型」「成果報酬型」の3種類であり、場合によってはそれらを組み合わせて契約がおこなわれます。
「固定価格型」は予算を立てやすい反面、仕様変更に追加費用が発生しやすい特徴があります。続いて「時間単価型」は、柔軟に対応できるものの、稼働時間が膨らむと費用が高くなるリスクがあります。そして「成果報酬型」は、開発成果に応じて費用が変動するため、リスクを分散できる点が特徴です。
SaaS開発会社を選ぶ際は、どの契約形態であっても、見積もりの内訳や追加費用の条件を事前に明確化しておくことが大切です。
過去のSaaS開発実績や得意分野は、システム開発会社の強みを知るための重要な判断材料です。
自社と同じ業界や同規模のサービスで成功事例があるシステム開発会社は、要件定義から運用までスムーズに進めやすくなります。特にSaaS開発では、「マルチテナント」「サブスクリプション課金」「API連携」など特有の要件が多く存在するため、これらの対応実績があるか確認しておきましょう。
公式サイトや事例紹介ページをチェックして、自社のニーズに近いプロジェクトを手がけた経験があるかを見極めることが安心につながります。
SaaSのプロジェクトを円滑に進めるためには、どのような開発体制で進められるかを確認しておくことが不可欠です。国内での開発体制かオフショア体制かによって、コミュニケーションのスピードやコストが変わります。
また、専任のプロジェクトマネージャー(PM)が配置されるかどうかも重要な要素です。PMが間に入ることで進捗管理や仕様調整がスムーズにおこなわれ、発注側の負担も軽減されます。
加えて、ウォーターフォール型かアジャイル型かといった、開発の進め方の違いも確認しておくと、期待する成果とのズレを防げます。
SaaSはリリースして終わりではなく、継続的な改善と安定運用が求められるサービス形態です。そのため、システム開発会社がどこまで運用保守をサポートしてくれるのかを契約前に確認することが欠かせません。
代表的なサポート内容には、バグ修正、機能追加、セキュリティアップデート、稼働監視などがあります。契約範囲が不明確だと、リリース後のトラブル発生時に迅速に対応してもらえず、利用者に不便を与えるリスクがあります。
サービス品質を安定させるためにも、事前に保守範囲・対応時間・追加費用の有無を明確にしておきましょう。
SaaSでは、利用者の個人情報や決済データを扱うケースが多いため、セキュリティと法令遵守は最優先で確認すべきポイントです。
具体的には、ISMSやプライバシーマークの取得状況、データ暗号化やアクセス制御などの技術的対策が整っているかを確認しましょう。また、個人情報保護法をはじめ、金融業界や医療業界など特定業界での規制に対応できるかも重要です。
これらの基準を満たしていないと、リスクだけでなく事業継続性にも影響を及ぼす可能性があります。安心してSaaS事業を展開するためにも、セキュリティとコンプライアンス対応力のあるシステム開発会社を選ぶことが大切なのです。
今回は、SaaSの概要や開発プロセス、個人開発の可否、システム開発会社を選ぶ際のポイント、そしておすすめのSaaS開発会社についてご紹介しました。
SaaS開発は、継続的な運用と改善を前提とするため、技術力だけでなくセキュリティや法令遵守、運用保守の体制など多面的な視点が必要です。事業化を目指す場合は、個人や自社だけで取り組むよりも経験豊富なSaaS開発会社と連携する方が、リスクを抑えながら成功につなげやすいでしょう。
自社の目的や業界特性、予算に合ったパートナーを選ぶことが、SaaS開発を軌道に乗せる最大のポイントです。今回の内容を参考に、信頼できるシステム開発会社と協力し、自社の成長を支えるSaaSサービスを構築していきましょう。