インフルエンサーマーケティングとは?メリットも解説
2021/09/14(火)

日本企業におけるシステム開発のニーズが多様化するなか、近年注目を集めているのが「ラボ型開発」です。通常の請負開発とは異なり、専属チームを一定期間確保することで、柔軟かつ継続的な開発体制を構築できる点が評価されています。
特に、新規サービスの立ち上げなどの長期プロジェクトにおいては、多くの企業がラボ型開発を選択肢の一つとして検討するようになっています。
本コラムでは、ラボ型開発の基本的な仕組みや、メリット・デメリットなどをわかりやすく解説し、最後はラボ型開発に強みを持つおすすめのシステム開発会社10社を厳選してご紹介します。
ラボ型開発を検討している担当者の方は、ぜひ参考になさってください。
【関連記事】
東京都でおすすめのシステム開発会社35選!【2026年最新】

ラボ型開発とは、発注企業がシステム開発会社と契約を結び、一定期間・一定コストで専属の開発チームを確保する形態の開発モデルです。
このモデルは、開発チームをあたかも自社の一部のように機能させることができるため、継続的なシステム開発や保守運用といった長期的な取り組みに適しています。特に近年では、システム開発において高い柔軟性が求められており、発注側と開発側が密に連携しながら進められるラボ型開発が注目されるようになりました。
ラボ型開発は、オフショア開発(海外拠点を活用した開発)の手法としても広く採用されてきました。しかし近年では、国内にもラボ型を展開する企業が増えており、言語や文化のギャップなく進められる国内ラボへの注目も高まっています。
ラボ型開発と混同されがちなのが、「SES(システムエンジニアリングサービス)」です。どちらも人材リソースを確保する契約モデルであるものの、働き方や契約形態には明確な違いがあります。
ラボ型開発では、専属の開発チームが開発会社側のオフィスに常駐して開発を進めるのが一般的で、発注企業はリモートでマネジメントしながら、チームと継続的に連携を取りつつプロジェクトを推進します。
一方、SESはエンジニアが基本的にクライアント(発注企業)のオフィスに常駐し、業務を遂行するモデルです。開発会社の管理下ではなく、発注側の現場で働くことになるため、派遣に近い形での稼働となります。

ラボ型開発と聞くと、「海外の開発拠点で行うオフショア型」というイメージを持つ方も多いかもしれません。
実際、ラボ型はもともとコスト面の利点から、東南アジアや中国など海外拠点での開発手法として普及してきました。しかし近年では、国内にもラボ型の開発体制を提供する企業が増えてきています。
ここでは、国外と国外それぞれのラボ型開発について、詳細を確認していきましょう。
国外ラボ型開発とは、ベトナムやフィリピン、インドなどの海外拠点に開発チームを構築し、ラボ契約に基づいて開発を進めるモデルです。
国外ラボ型開発では、日本国内に比べて開発コストを大幅に抑えられ、一定の品質を保ちながらもコストパフォーマンスに優れた開発体制が構築できます。
その一方で、言語や時差、文化的背景の違いがプロジェクト進行に影響を与えるケースもあります。そのため、オフショア先とのコミュニケーションを円滑に保つための体制構築が重要です。
国内ラボ型開発は、日本国内に拠点を持つ開発会社とラボ契約を結び、同一の文化・言語・タイムゾーンのもとで専属開発チームを運営するモデルです。
最大のメリットは、コミュニケーションのしやすさとプロジェクトの透明性にあります。進行中のトラブルにも迅速に対応でき、仕様変更やレビュー依頼といった細かな調整もスムーズにおこなえます。
また、国内の開発企業であれば、品質管理やセキュリティ面での不安も少なく、法務対応や契約管理も日本基準で統一できます。そのため、安心して長期契約を結びやすいのも魅力です。

ラボ型開発は、従来の請負契約やSESとは異なる柔軟な開発体制を実現できる点で、多くの企業や開発会社から注目を集めています。
ここでは、ラボ型開発を導入することで得られる主なメリットを4つご紹介します。
ラボ型開発では、発注企業がシステム開発会社とラボ契約を結び、一定期間専属の開発チームを確保できます。これにより、プロジェクトの立ち上げから保守運用まで一貫して対応できる体制を構築でき、継続的な開発が可能になります。
特に、同じメンバーでプロジェクトを継続できる点は、開発の属人化や引き継ぎによるミスのリスクを抑える効果があります。
ラボ型開発では、専属の開発チームを確保しながらも、自社で人材を採用・教育・管理する手間やコストを抑えられます。
特にオフショア(国外)ラボ型開発の場合は、人件費そのものを大幅に削減できるのが魅力です。一方、国内ラボ型であっても、地方拠点やフリーランス活用型など柔軟な体制を持つ会社を選べば、コストパフォーマンスの高い開発が可能になります。
ラボ型開発では、「期間×人数」での契約が基本となるため、契約期間内であれば仕様変更や機能追加にも柔軟に対応できます。
あらためて追加見積もりを出す必要がないケースも多く、開発スピードを維持したままプロジェクトを進めることが可能です。特にアジャイル開発と相性が良く、反復的に要件を見直しながら開発を進めるようなスタイルにも適応できます。
ラボ型開発では、同じ開発チームが継続的にプロジェクトに関わるため、細かなノウハウが自然とチーム内に蓄積されていきます。
例えば、新しい機能を追加する際やトラブル発生時にも、既存の知見を活かして迅速な判断が可能になります。こうした知識の蓄積は、保守や改修のフェーズにおいて大きな武器となり、長期的に見ても開発コストの削減につながります。

ラボ型開発には多くのメリットがある一方で、導入にあたっては注意すべきポイントも存在します。
ここでは、ラボ型開発を検討する際に知っておきたい代表的なデメリットを3つご紹介します。
ラボ型開発は、「作業時間×人数」という形で専属チームの稼働を契約するため、タスクが一時的に発生しない期間であっても、契約期間中の費用は発生し続けます。これは、プロジェクトの進捗や開発ボリュームの見通しが甘い場合、稼働率が低下し、結果的にコストパフォーマンスが悪化するリスクを意味します。
例えば、発注企業側の社内都合で要件定義や意思決定が滞ると、チームが手待ち状態になり、稼働していないのにコストだけがかかるという事態も起こり得ます。こうした無駄を避けるためには、発注前の段階で「どの時期に・どの業務を・どの程度任せるか」といった発注計画をしっかりと立てておくことが重要です。
ラボ型開発では、専属チームを新たに立ち上げることが多いため、初期段階での準備にある程度の時間を要します。具体的には、適切なスキルを持つメンバーのアサイン、業務内容のレクチャー、開発フローの共有、コミュニケーション体制の整備などが必要です。
特にオフショアの開発会社を利用する場合は、言語の壁や開発文化の違いなどを乗り越えるために、十分なオンボーディングやマニュアル整備が求められます。短期的な開発には不向きな側面もあるため、一定以上の期間とスパンで開発を進めるプロジェクトに適しているといえるでしょう。
ラボ型開発では「成果物ベース」ではなく、「プロセスベース」での運用が基本となります。そのため、開発会社に任せきりにするのではなく、発注企業側にも日常的なマネジメントやディレクション業務が発生します。
例えば、進捗管理、仕様のすり合わせ、レビュー、優先順位の調整、技術的な意思決定など、継続的に関与する必要があります。
そのため、ラボ型開発を導入する際は、単に開発リソースを外注するのではなく、パートナー会社と協働するという意識を持つことが大切です。

ここでは、ラボ型開発を成功させるため、開発会社を選定する際に確認しておきたいポイントを4つご紹介します。
まず大切なのは、「なぜラボ型開発を選ぶのか」という目的意識です。新規開発か、既存サービスの保守運用か、社内で対応しきれない部分の補完かなど、活用シーンを明確にしましょう。
発注ボリュームや優先度も事前に整理しておくことで、無駄な待機時間を減らし、開発会社の稼働率を高く保てます。
海外の開発会社を利用する場合は特に、言語・時差・文化の壁を乗り越える体制があるかをチェックしましょう。
日本語対応が可能か、ブリッジSEや専任のプロジェクトマネージャーが配置されるかなど、コミュニケーション品質に直結する要素は必ず確認しておきたいポイントです。国内会社の場合も、担当の配置や報連相の仕組みを明確にしておくと安心でしょう。
信頼できる会社かどうかを見極めるには、これまでのラボ型開発の実績や、長期契約の継続率が重要な判断材料になります。
同業種や同規模の企業との事例が豊富な会社であれば、ノウハウの共有もスムーズで、安心して開発を任せられるでしょう。特に、継続的に契約更新されているかどうかは、その会社の対応力や満足度を知るうえで有効です。
ラボ型は「人と時間」の契約になるため、成果物の権利関係は曖昧になりがちです。そのため、開発会社との間で、著作権や納品形式、コードの所有権について明確にしておくことがトラブル回避につながります。
あわせて、NDA(秘密保持契約)やセキュリティ対策なども契約書レベルで確認し、安心して開発を委託できる体制を整えましょう。
ラボ型開発を導入するにあたって最も重要なのが、信頼できる開発会社の選定です。
ここでは、ラボ型開発に強みを持つシステム開発会社を厳選してご紹介します。それぞれの会社の特徴や対応スタイルを比較しながら、自社に合ったパートナー選びの参考になさってください。

フレシット株式会社は、国内に拠点を構えるシステム開発会社として、柔軟性の高いラボ型開発サービスに定評があります。単発の開発にとどまらず、継続的な運用や改善を見据えた体制構築を得意としている点が、多くの企業から選ばれている理由です。
スモールスタートでの検証フェーズから、本格的な大規模開発まで幅広く対応できるため、事業フェーズや予算に応じた無理のない開発が可能。状況に合わせて開発体制を柔軟に調整できる点も、大きな強みです。
開発は、業務理解に優れたプロジェクトマネージャーを中心に、案件ごとに最適なメンバーでチームを編成。丁寧なヒアリングをもとに、設計・開発・運用までを一気通貫で対応するため、要件が固まりきっていないプロジェクトや、途中で仕様変更が発生しやすい案件でも安心して任せることができます。
「長く付き合える開発パートナーを探している」「事業の成長に合わせて柔軟にシステムを育てたい」
そんな企業にとって、フレシット株式会社は信頼できる存在となるでしょう。

画像出典:https://www.aris-kk.co.jp/
株式会社アリスは、「ラボ型開発」を主軸にサービスを展開する注目の開発会社です。
これまでの豊富なオフショア開発の実績を活かし、IT活用やビジネス拡大に関するさまざまな課題を解決してきました。
日本人スタッフによる丁寧なフォローと、ベトナムの高い技術力を融合させることで、お客様のビジネスを力強くサポートしている点が高く評価されています。

株式会社YAZは、全国に拠点を持ち、すべての開発業務を国内で完結させているシステム開発会社です。東京・札幌・新潟・名古屋を中心に、地域分散型のラボ型開発体制を展開しており、安定した品質と柔軟な対応力に定評があります。
クラウド基盤やスマホアプリ、業務系システムなど多岐にわたる技術領域に対応しており、自社ビジネスに合わせた最適なIT活用をサポートしてくれます。

画像出典:https://www.i-enter.co.jp/
株式会社アイエンターは、「i-Labo」という独自のラボ型開発サービスを展開するシステム開発会社です。
目的に応じて「グロース型」と「技術提供型」の2種類のラボ契約を選んで利用できます。
国内外に拠点を持ち、初期投資を抑えながら仕様変更に柔軟に対応できる体制が整っており、KPI重視のプロジェクトやチーム単位での技術支援にも強みを発揮します。
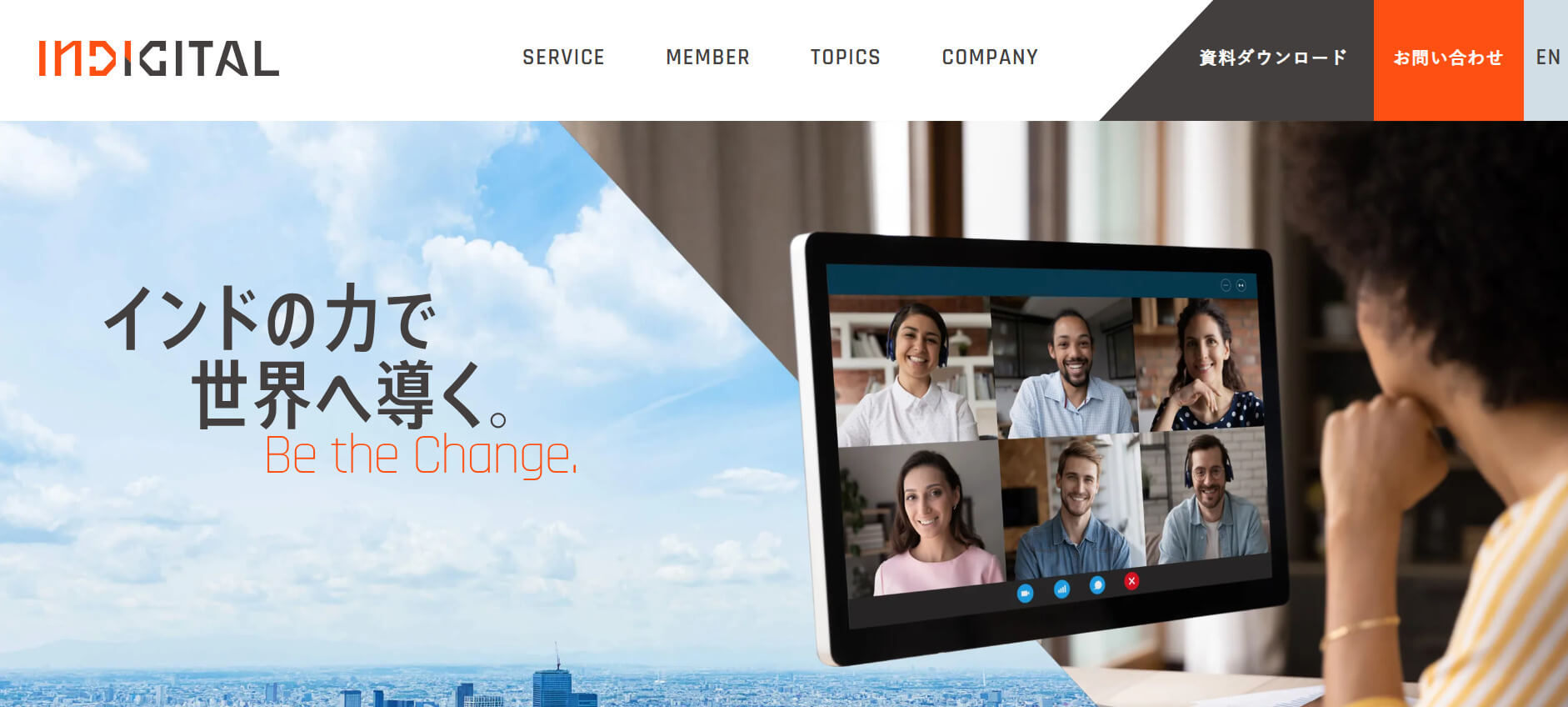
株式会社INDIGITALは、インド拠点の強みを活かしたラボ型開発サービスを提供するシステム開発会社です。
高い技術力と英語力を備えた現地エンジニアと連携しながら、コストを抑えた柔軟な開発体制を構築できる点に定評があります。
Web3やAIなど先端領域にも強く、日本語対応が可能な体制や文化理解を前提としたプロジェクトマネジメントにも対応しています。
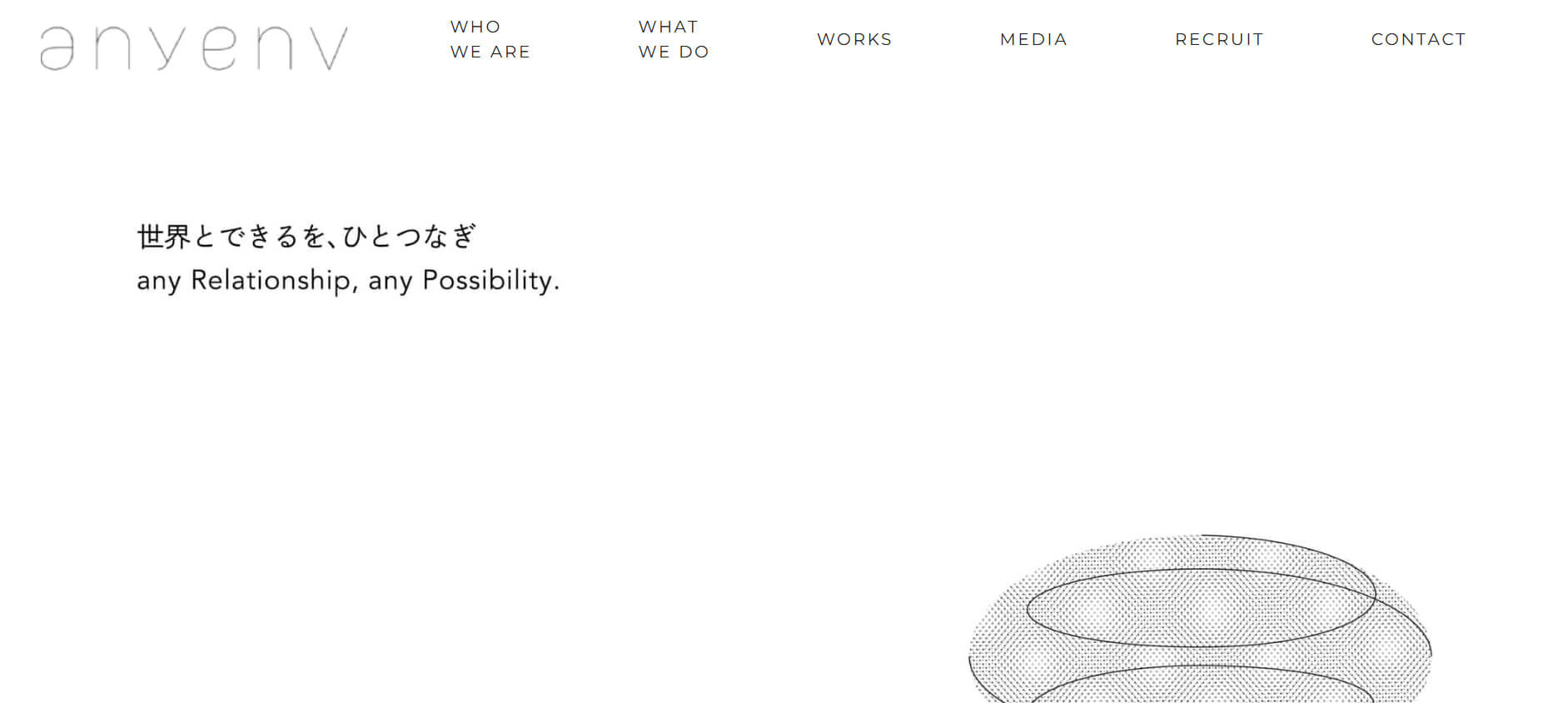
画像出典:https://www.anyenv-inc.com/
anyenv株式会社は、東京を拠点に全国6都市へ展開し、グローバル開発にも力を入れるシステム開発会社です。
インドに設立した開発拠点では、AIやビッグデータ解析など先端技術に強い現地エンジニアが在籍しており、高度な技術とコスト競争力の両立を実現しています。
日本人スタッフが現地にも常駐しており、海外開発に不安がある企業でも安心して任せられる体制です。

画像出典:https://www.sateraito.jp/
株式会社サテライトオフィスは、ベトナム・ホーチミンとハノイに開発拠点を持ち、東京に本社を構えるオフショア開発会社です。
アジャイル開発を採用しており、業務システムからアプリ開発まで幅広く対応し、スピード感のある開発とコストパフォーマンスに強みがあります。
日本人社員による窓口対応もあるため、語学面が不安な企業にもおすすめです。
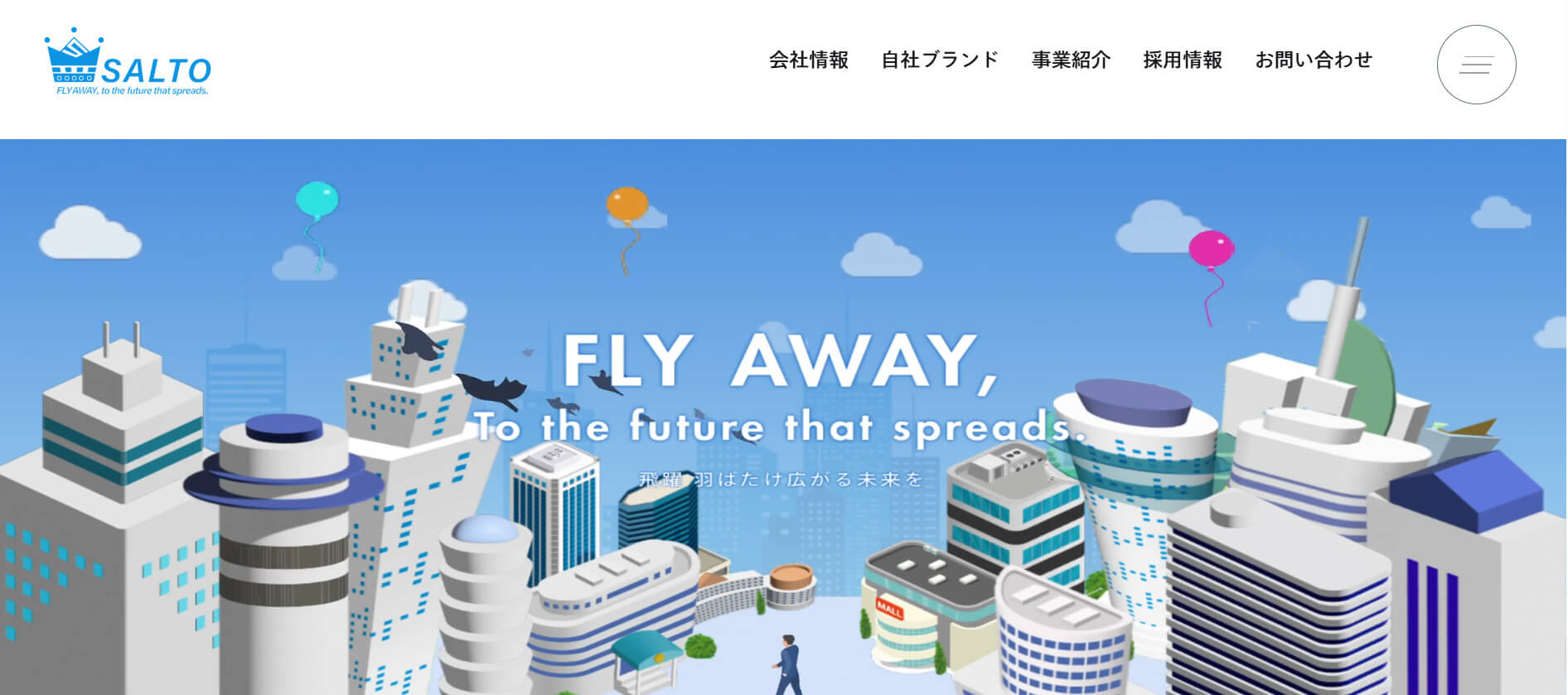
画像出典:https://salto.site/
株式会社SALTOは、東京・大阪・ベトナムに拠点を構えるシステム開発会社で、柔軟かつ中長期的なラボ型開発に対応しています。
コミュニケーション力と技術力を備えたマネージャーが検収基準を設け、毎月の成果を可視化しながら安定した開発を実現する体制が特徴です。
ニーズに応じて国内外の拠点を使い分けられ、品質を重視する企業からコストを抑えたい企業まで幅広く対応しています。

Bee Tech Asia株式会社は、ベトナム・ハノイを拠点に、東京・千葉にもオフィスを展開するグローバルなシステム開発会社です。
自動化やモダンな開発体制を積極的に導入し、エンジニアの継続的な学習体制にも力を注いでいます。
大手決済アプリの継続開発をはじめ、長期的な契約実績も豊富にあり、品質とコストのバランスを重視する企業にとって、信頼性の高い開発会社といえるでしょう。

画像出典:https://www.playnext-lab.co.jp/
プレイネクストラボ株式会社は、国内外の優秀なエンジニアを活用し、日本企業の開発課題に応えるハイブリッド型のラボ開発に強みを持つ会社です。
東京・品川に本社を構え、エンジニアの8割以上が外国人という国際色豊かな開発体制に特徴があります。
オフショア×国内開発で最適化を図り、人材マッチングも支援する柔軟かつ実績豊富な開発会社です。
今回は、ラボ型開発の特徴やメリット・デメリット、依頼時のポイント、そしておすすめの開発会社についてご紹介しました。
ラボ型開発は、一定期間・一定コストで専属チームを確保できる契約形態であり、要件の変化や開発体制の柔軟性に対応したい企業にとって非常に有効な選択肢です。ただし、明確な役割分担や進行管理が伴わないと、期待した効果が得られない可能性もあります。
そのため、導入前には自社の目的や体制に合っているかを見極め、信頼できる開発パートナーと連携していくことが重要です。
今回の内容を参考に、自社の成長を支える最適な開発体制を構築していきましょう。